こんにちは、
ともやんです。
今年の6月にカラヤンの新しいアルバムが発売されました。
そのCDのタイトルが『ねむりのカラヤン』
つまりこのアルバムのコンセプトは、これを聴くと心がやすらぎ、眠りに誘われてしまうというものらしい。
昨年の11月に同様の目的で『ねむりのビル・エヴァンス』が発売されています。
多分、それが好評だったのでしょう。
そして二匹目のドジョウを狙って発売されたのが『ねむりのカラヤン』というわけだ。
では、このCDを聴くと本当に眠くなってしまうのか、と実際に聴いてみて、意外な発見をしたのです。
ねむりのカラヤン収録曲をチェックする
アルバム「ねむりのカラヤン」の収録されている曲は、以下の11曲。
いかにもタイトルを聴いただけで眠くなりそうな作品が並んでいます。
パッフェルベル:カノン
ヨハン・パッヘルベル – Johann Pachelbel (1653-1706)
1.(05:02) カノンとジーグ ニ長調(M. ザイフェルトによるチェンバロと管弦楽編)
Canon and Gigue in D Major (arr. M. Seiffert for harpsichord and orchestra)
編曲 : マックス・ザイフェルト – Max Seiffert
フランク・マウス – Frank Maus (チェンバロ)
第1曲目のまさに定番ともいうべき「パッヘルベルのカノン」。
ヨハン・パッヘルベルは、17世紀後半から18世紀初頭に活動していたドイツの作曲家。教会音楽や室内楽の重要な作曲家だったそうだが、いまではこのカノンだけが圧倒的に有名で、いろんな形で編曲されて親しまれています。
自筆譜はないということですが、オルガンで演奏されたものが僕は好きですね。
ペール・ギュント:ソルヴェイグの歌
エドヴァルド・グリーグ – Edvard Grieg (1843-1907)
2.(06:15) ペール・ギュント 組曲第2番 Op. 55 – 第4曲 ソルヴェイグの歌
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55 IV. Solveig’s Song
グリーグは、ノルウェーの民族音楽からインスピレーションを得た民族主義的な作曲家として有名。ペール・ギュントは、彼の代表作。第4曲のソルヴェイグの歌は、その清澄な空気感がいいですね。
マスネ:タイスの瞑想曲
ジュール・マスネ – Jules Massenet (1842-1912)
3.(06:00) 歌劇「タイス」 – 第2幕 瞑想曲
Thais, Act II: Meditation
ミシェル・シュヴァルベ – Michel Schwalbe (ヴァイオリン)
録音: September 1967, Jesus-Christus-Kirche, Berlin, Germany
ヴァイオリニストの小曲集などのアルバムには必ずと言っていいほど収録されている作品。
ソロを弾くのが、カラヤン時代を支えてコンサートマスターのシュヴァルベ。
マスカーニ:歌劇より間奏曲
ピエトロ・マスカーニ – Pietro Mascagni (1863-1945)
4.(03:29) 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」 – 間奏曲
Cavalleria rusticana: Intermezzo sinfonico
ヴォルフガング・マイヤー – Wolfgang Meyer (オルガン)
録音: September 1967, Jesus-Christus-Kirche, Berlin, Germany
マスカーニ (1863-1945) プロフィール HMVオンライン
↑
イタリアの作曲家ピエトロ・マスカーニ(1863-1945)のプロフィールです。
なかなか波乱に富んだ生涯を送った方で、また改めて深掘りしたいと思います。
ビゼー:アルルの女組曲第2番より
ジョルジュ・ビゼー – Georges Bizet (1838-1875)
5.(03:57) アルルの女 組曲第2番 – 第3曲 メヌエット(E. ギローによる管弦楽編)
L’Arlesienne Suite No. 2: III. Minuetto (arr. E. Guiraud for orchestra)
編曲 : エルネスト・ギロー – Ernest Guiraud
ダニエル・デファイエ – Daniel Deffayet (サクソフォン)
録音: December 1970, Jesus-Christus-Kirche, Berlin, Germany
今月ビゼーの歌劇「カルメン」のコンサート版に合唱団の一員として参加しました。
歌詞がフランス語で苦労しましたが、なんとかステージに立つことが出来て良かったです。
「カルメン」は、ビゼー最後のオペラで、初演から僅か後に急逝しています。知れば知れ程傑作だと思います。天才肌の作曲家で、「アルルの女」はその中でも特に有名な作品ですね。
プッチーニ:修道女アンジェリカより
ジャコモ・プッチーニ – Giacomo Puccini (1858-1924)
6.(04:32) 歌劇「修道女アンジェリカ」 – 間奏曲
Suor Angelica: Intermezzo
録音: September 1967, Jesus-Christus-Kirche, Berlin, Germany
ショパン:バレエ「レ・シルフィード」
フレデリック・ショパン – Fryderyk Chopin (1810-1849)
7.(05:50) バレエ音楽「レ・シルフィード」 – 夜想曲第10番 変イ長調 Op. 32, No. 2 (R. ダグラスによる管弦楽編)
Nocturne No. 10 in A-Flat Major, Op. 32, No. 2 (arr. R. Douglas for orchestra) [Les Sylphides]
編曲 : ロイ・ダグラス – Roy Douglas
モーツァルト:ディヴェルティメント
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト – Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
8.(07:13) ディヴェルティメント第15番 変ロ長調 K. 287 – 第4楽章 アダージョ
Divertimento No. 15 in B-Flat Major, K. 287: IV. Adagio
バッハ:G線上のアリア
ヨハン・ゼバスティアン・バッハ – Johann Sebastian Bach (1685-1750)
9,(05:59) 管弦楽組曲第3番 ニ長調 BWV 1068 – 第2曲 エール「G線上のアリア」
Overture (Suite) No. 3 in D Major, BWV 1068: II. Air, “Air on the G String”
デイヴィッド・ベル – David Bell (オルガン)
ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ
モーリス・ラヴェル – Maurice Ravel (1875-1937)
10.(07:04) 亡き王女のためのパヴァーヌ(管弦楽版)
Pavane pour une infante defunte (version for orchestra)
録音: December 1985, Philharmonie, Berlin, Germany
マーラー:交響曲第5番より
グスタフ・マーラー – Gustav Mahler (1860-1911)
11.(11:53)交響曲第5番 嬰ハ短調 – 第4楽章 アダージェット
Symphony No. 5 in C-Sharp Minor: IV. Adagietto
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 – Berlin Philharmonic Orchestra
ヘルベルト・フォン・カラヤン – Herbert von Karajan (指揮)
ヴィスコンティ監督の映画「ベニスに死す」(1971年)に使われた曲として有名です。
バッハのG線上のアリア、ラヴェルの亡き王女のためのパヴァーヌ(管弦楽版)でほぼ眠くなってきますが、この作品意外と複雑な作品で、私などは聴いていてかえって目が冴えてしまうんですね。
ねむりのカラヤン ヘルベルト・フォン・カラヤン 、 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
楽壇の帝王 ヘルベルト・フォン・カラヤンの美しい癒しの名曲をコンパイルしたコンピレーション・アルバム!
昨年末にリリースし好評を博しているコンピレーション『ねむりのビル・エヴァンス』のクラシック版、第1弾。
20世紀楽壇の帝王ヘルベルト・フォン・カラヤンが遺した膨大なクラシックの名演から、美しく「心に安らぎを与える」名曲をコンパイル。
まとめ
「ねむりのカラヤン」というタイトルを聞いて、カラヤンの演奏ならまさに打ってつけのタイトルと直感しました。
ねむりたいのなら、やっぱりカラヤンだよね、とも思いました。
それほどカラヤンの演奏は心地よいのです。
ただ、これが僕にはカラヤンの弱点とも言えます。
僕はカラヤンの演奏では嫌いではありません。
特に60年代までの演奏は素晴らしいと思います。
しかし、ベルリン・フィルとの関係が長く続くにしたがい、なぜかつまらなくなって来たのです。
つまり眠りに打ってつけとは、心地よいのとつまらないは、紙一重ということです。
このCDの演奏から、何を感じるか人それぞれかなと思います。
ぜひ聴いてみてください。
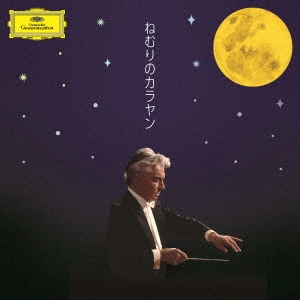
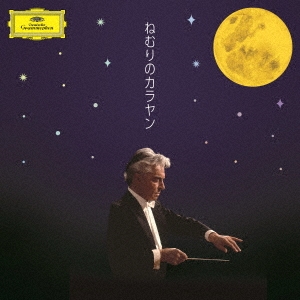


コメント