こんにちは、
ともやんです。
先日、ブルックナーの交響曲第1番を取り上げて、今年生誕110年を迎えた二人に偉大な指揮者、ヘルベルト・フォン・カラヤンと朝比奈隆の演奏の聴き比べを書きました。
意外と好評でしたので、この企画を続けたいと思います。
僕もそうですが、クラシック音楽ファンの人たち、特に男性諸氏は、聴き比べが好きです。
僕が現在所属する合唱団のメンバーともよく、例えばベートーヴェンの英雄は、誰誰の演奏がいいね、なんてよくしています。
さて、そこで今日は人気曲、ブラ1こと、ブラームス交響曲第1番を取り上げます。
↑ ↑ ↑
先日、朝比奈の全集盤を取り上げたばかりですが、参照頂ければ幸いです。
1978年 カラヤンとベルリンフィルとの関係に暗雲
1959年からベルリンフィルのインテンダントを務めていたのが、シュトレーゼマンという言う人で、カラヤンより4歳年上でした。
オーケストラのインテンダントという立場は、総支配人、総裁、またが事務局長とも訳され、オーケストラの運営面の最高責任者です。
つまり、カラヤンがベルリンフィルの首席指揮者に就任してからは、音楽面ではカラヤンが、運営面ではシュトレーゼマンが担当していてわけです。
シュトレーゼマンは、気まぐれなカラヤンを上手くコントロールして、くぎを刺す部分がビシッと言ったりとカラヤンの暴走にブレーキを掛けていました。
だからオーケストラの団員からも信頼が厚かったのです。
しかし、1978年にシュトレーゼマンが、74歳で惜しまれながら勇退するとカラヤンとは親子ほども違うギルトという人がインテンダントに就任しました。
ギルトもベルリンフィルのインテンダントになる人ですから、相当優秀な人と思われますが、シュトレーゼマンほどカラヤンをコントロールできず、カラヤンは運営面にも口を出すようになってきました。
そうなるとオーケストラのメンバーからも不満が出ます。
それが後年のカラヤンとベルリンフィルの軋轢に発端だったと思います。
しかし、このブラームス交響曲が録音された1977年から78年は、シュトレーゼマン最後の頃でカラヤンとベルリンフィルは、圧倒的なパワーで迫ってきます。
ブラームス交響曲第1番 カラヤン&ベルリンフィル
ヨハネス・ブラームス – Johannes Brahms (1833-1897)
交響曲第1番 ハ短調 Op. 68
Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68
1.(13:11)I. Un poco sostenuto – Allegro
2.(08:50)II. Andante sostenuto
3.(04:41)III. Un poco allegretto e grazioso
4.(17:24)IV. Adagio – Piu andante – Allegro non troppo ma con brio
total(44:06)
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 – Berlin Philharmonic Orchestra
ヘルベルト・フォン・カラヤン – Herbert von Karajan (指揮)
録音時期:1977-78年
録音場所:ベルリン、フィルハーモニー
録音方式:ステレオ(セッション)
ブラームス: 交響曲全集 ヘルベルト・フォン・カラヤン ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
カラヤンがベルリン・フィルを自在に操って聴かせるブラームス。このコンビ2度目の全集録音で、彼らの黄金時代ともいうべき時期の録音だけに、カラヤンの巨匠性が強烈に表現された、堂々たる演奏になっています。タワーレコード (2009/04/08)
カラヤン&ベルリン・フィルの黄金時代、1970年代半ばに収録された強烈な演奏で、そのあきれるばかりのブリリアント・サウンドには、やはり抗いがたい魅力があります。
とにかく、4つのシンフォニーのどこを取っても自信みなぎる響きと表情に満ちあふれた演奏で、第1番の壮麗な威容は比類ないものですし、第4番でも確信にみちた輝かしいサウンドが一貫しています。この4作品をあくまでもドイツ・ロマン派シンフォニーの傑作として捉えたアプローチと、ベルリン・フィルの重厚華麗なサウンドが相まったその聴き応えには、脱帽するほかありません。
オーケストラ音楽とはこうあるべきというカラヤンの信念がビシビシ伝わってくるゴージャスきわまりない演奏です 。HMV
ブラームス交響曲第1番 朝比奈隆&新日本フィルの剛毅
ヨハネス・ブラームス – Johannes Brahms (1833-1897)
交響曲第1番 ハ短調 Op. 68
Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68
1.(16:53)I. Un poco sostenuto – Allegro
2.(08:02)II. Andante sostenuto
3.(04:54)III. Un poco allegretto e grazioso
4.(16:51)IV. Adagio – Piu andante – Allegro non troppo ma con brio
total(46:40)
新日本フィルハーモニー交響楽団 – New Japan Philharmonic Orchestra
朝比奈隆 – Takashi Asahina (指揮)
録音: 11 September 2000, Suntory Hall, Tokyo, Japan
ブラームス:交響曲第1番 – 第4番(新日本フィル/朝比奈隆)(2000-2001)
最晩年の朝比奈隆の演奏は、巨大な造形は不変ながら、”ルパートを排し、収斂したテンポで音楽を統一する”という境地に達していました。
勿論、こちらのブラームスも例外ではなく、終演後に楽屋を訪れた金子建志氏が、テンポに関して質問すると、巨匠は以下の様に答えました。
「今回、たまたまクレンペラーの録音を聴きなおしてみたんですよ。これが、速いテンポでなかなかいい。フルトヴェングラー先生の真似をすると、色々と問題が多いのだけれど、クレンペラーならいいのではないかと思ってね。」
金子氏は、「これを先生一流のリップ・サーヴィスと受け流すだけでなく、常に試行錯誤を繰り返しながら演奏に臨んでいる現役の演奏家ならではの言葉と捉えることも必要なのではあるまいか。」と述べておられます。タワーレコードより
まとめ
カラヤンと朝比奈の共通点は、二人とも音楽に対して真摯に接し、決して変な演奏をしなかったことだと思います。
常に真面目に作曲者のスコアに対応し、スコアを信じその音楽を再現したことだと思います。
カラヤンに対してアンチ・カラヤンという人たちもいましたが、僕はカラヤンの演奏を聴いていてこれが一番感心しています。
常に真面目に音楽に取り組み、へんちくりんな表現とか、驚かせてやろうとかという表現は一切見受けられません。
朝比奈隆も同じで、ご本人も自分は職人と言っておられますが、まさに職人魂を追求した演奏で、内声部や伴奏部分を聴くと疎かにせず、しっかり弾くという信念が伝わってきます。
でも、出てくると音楽は、カラヤンの高級ブランドのスーツに身を包み一瞬の隙もないビジネスマンで朝比奈の和服を着こなした凛として粋な国宝級の役者という違いを感じます。
だから聴き比べは止められません!
![]()
音楽(クラシック) ブログランキングへ
↑
クリック応援お願いします。

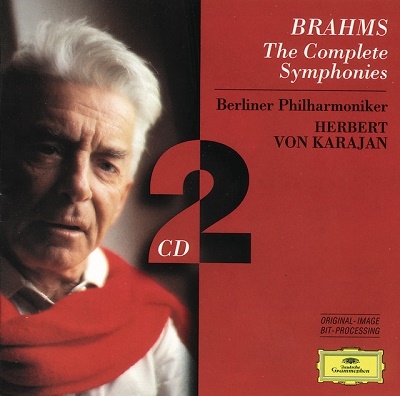

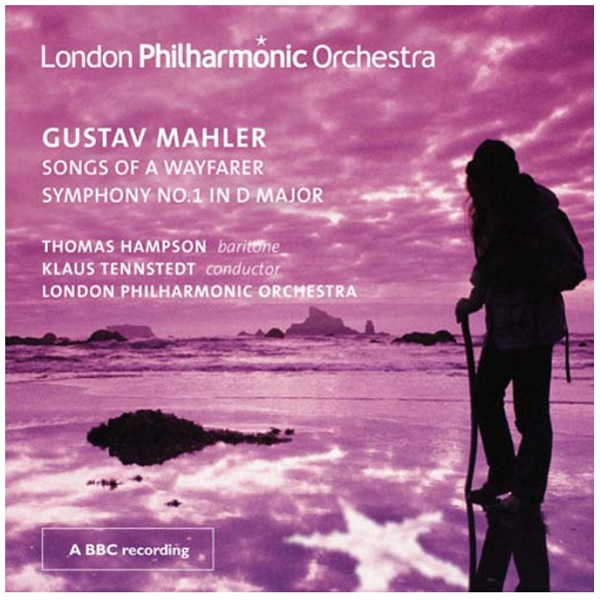
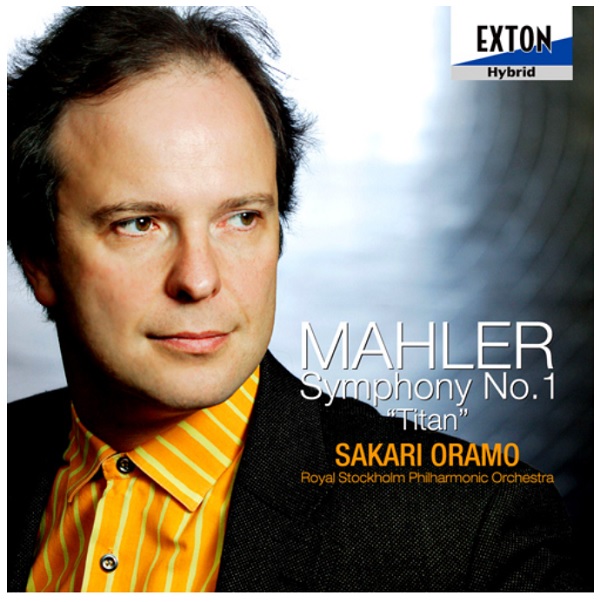
コメント