こんにちは、
ともやんです。
クレンペラーのブルックナーは、後年のフィルハーモニア管との録音では、例えば第5番などは、まるで大河の流れのような悠然たる演奏を展開しています。
しかし、60年代の初めころまでは、どちらかという早めのテンポで素っ気なく展開する演奏が多いように思います。
そこで50年代にブルックナー第7番をウィーン交響楽団と演奏して録音のレビューしたいと思います。
クレンペラーが指揮するブルックナー
確か、第4番“ロマンティック”では、最短の演奏を残しているのもクレンペラーだったと思います。
その辺のクレンペラーの芸術の変遷は、とても興味深く、僕はそのうちクレンペラーの全録音を聴いて、ブログにまとめたいと思っています。
まあ、現在のフルタイプ勤務から解放されてからですが。。。
さて、今日は、1958年2月23日のウィーン交響楽団とのコンサートからの実況録音です。
1950年代のクレンペラーは、51年にモントリオール空港でタラップから転落して大けが。
回復した後もパスポート問題でアメリカから出国できないなどトラブル続きでした。
しかし、1953年頃からヨーロッパ中心での活躍も順調に来ていた時期の録音です。
クレンペラー ブルックナー 交響曲第7番
アントン・ブルックナー – Anton Bruckner (1824-1896)
交響曲第7番 ホ長調 WAB 107
Symphony No. 7 in E Major, WAB 107
Ⅰ(18:16)Allegro moderato
Ⅱ(19:45)Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam
Ⅲ(09:10)Scherzo: Sehr schnell
Ⅳ(12:37)Finale: Bewegt, doch nicht schnell
total(64:50)
ウィーン交響楽団 – Wiener Symphoniker
オットー・クレンペラー – Otto Klemperer (指揮)
録音:1958年2月23日(ライヴ)
ブルックナー:交響曲 第7番 ホ長調 【演奏】オットー・クレンペラー指揮ウィーン交響楽団
クレンペラーという人は、なにかと大きなケガやトラブルに巻き込まれた方です。
しかし、この58年という時期は、モントリオール空港での転落事故やパスポート更新問題も乗り越えて、53年頃から活躍の場を広げて、5年ほど経った頃で、クレンペラーとしては充実していた時期と言えます。
このブルックナーの7番も壮年期の素っ気ない演奏から、かなり深みを増したものになっていて、第2楽章などは、ああ、ブルックナーっていいなぁ、なんて浸りたくなるような名演を展開しています。
ライブのモノラル録音ですが、音質はいいので、鑑賞に全く問題はありません。
クレンペラーとカラヤンの違い
「カラヤンとフルトヴェングラー」という本を読みました。
1930年代からフルトヴェングラーが亡くなる1954年過ぎまでのベルリンフィルを巡る権力闘争を軸に、当時のナチス統治下のドイツにおける政治と芸術に関する音楽家たちの考え方の違いを描いた力作です。
著者は中川右介氏。
芸術家は、芸術的才能のみで通用する仕事はほとんどありません。
画家も小説家も詩人も、作曲家も演奏家も、ある程度プロデュース能力とマネージメントの力がないとそもそも自分を売り出したりすることも出来ないと思います。
その中でオーケストラの指揮者ほど、芸術以外の才能や能力が求められる仕事はないと思います。
オーケストラのメンバー、数十人から百数十人を統率する能力、聴衆を陶酔させる能力が必要で、凡人には出来ない仕事です。
カラヤンがフルトヴェングラー亡き後、ベルリンフィルの首席指揮者として終身契約が出来たのは、カラヤンが音楽的才能が他のライバルたちより優れていたからではありません。
そこには権謀術数を駆使したカラヤンのビジネスセンスと才能があったからに他なりません。
クレンペラーは偉大な芸術家だった
そんな指揮者の中でオットー・クレンペラーを聴くと、この人はどちらかというと、音楽的な才能を高く評価されて20世紀の大指揮者として名を連ねているのではないか、と僕は思ってしまいます。
ぶっきら棒で素っ気なく、人を人をと思わないその性格は、とてもカラヤンのように、うまく立ち回れる人とは思えないからです。
もちろん僕の推測ということを断っておきますが。
よくクレンペラーの演奏は、75才を過ぎた1960年代から深みを増し凄くなったと言われ、実際残されている録音には名演が多いと言われています。
もちろん録音技術が進んだのもひとつの理由とは思います。
でも一方で僕は、70歳代前半だった1954年から58年の演奏が、むしろ覇気や活気の面では、後年の1960年代よりも上ではないかと感じています。
まとめ
本日紹介するブルックナーの7番は、1958年、クレンペラー72才の時の演奏。
有名な寝たばこ大やけど事件があったのはこの年の9月です。
クレンペラーはその大やけどで1年ほど演奏も出来ず再起不能とも言われました。
もしそこで彼のキャリアが終わっていたら、埋もれた大指揮者としてだけ名を留めたでしょう。
逆にその大やけど事件がなければ、もっと活躍していたかもしれません。
どちらにしろ、この時期のクレンペラーの演奏は、武骨ながら覇気があり、内面から湧き出るような情熱も感じさせてくれます。
この時期のクレンペラーはもっと評価されてもいいかなと思いますね。


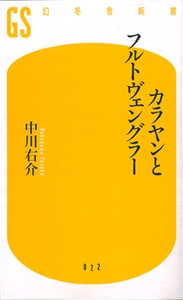


コメント